第7章 小角と前鬼・後鬼  BGM is playing now ! BGM is playing now ! |
|
■ 第25話 前鬼と後鬼のこと 1 ■ |
| |
解 説 |
|
|  |
前鬼と後鬼について、次の逸話も残っている。

父鬼は赤眼といい、母鬼は黄口といい、鬼一、鬼次、鬼助、鬼虎、鬼彦という五人の子どもがいた。
小角は、生駒の暗峠で鬼たちを見つけたが、なかなか捕まえられなかった。そこで、小角は、鬼たちを懲らしめるため、親鬼たちが一番かわいがっていた末の子=鬼彦を鉢の中に隠した。
鬼彦がいなくなり、土のよう顔色になった親鬼たちは、あちこち探しまわったが見つからなかった。
親鬼たちは、哀しみのあまり、遂に小角の前に出てきて「鬼彦がいなくなった。どうか、助けてくだされ。」と頼んだ。 |
|
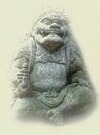
前鬼(男鬼) |

後鬼(女鬼)
|
小角は、「お前たちは、人の子を殺してばかりいるではないか! どうして、わが子ばかりをかわいがるのか!」と叱った。
すると、鬼親は「わしらは、元々、山にいる鳥や獣を捕って喰っていた。だが、近頃は、人間が大勢やって来て、わしらの食べ物を取ってしまう。それで、何もなくなってしもうた。ついつい、人の子を捕って喰うようになってしもうた。」と、泣きながら話した。

この時、突然、赤い炎を背にした不動明王が、眼をギラギラと光らせながら、雷のような音をたてて、空の上から現れてきた。
小角は、「お前たちは、心を改めて、人の子を取って食うような悪い事をするな! もしも悪いことばかりしていると、不動明王さまの怒りに触れるぞ。お前らのヘソはかじり取られてしまうぞよ。」と、大きな声で諭した。
鬼たちは、「食べ物がないと死んでしまう。どうか、良い知恵を授けてくだされ。」と、小角にすがった。
小角は、「もし、すっかり心を改めるなら、人間に変われるぞ。これから神呪を唱える。お前たちも一緒に唱えよ!」と、応えた。
鬼たちは、一生懸命神呪を唱えた。そして、鬼たちは、山伏姿に変わった。
| |
解 説 |
|
|  |
一般的に、役行者像は、前鬼と後鬼を従えている。
前鬼の善童鬼(ぜんどうき)は、陽を表す赤い色の鬼で、右手に鉄の斧をもち、背中に笈を背負っている。
頭は怒りの髪をなびかせ、口は固く吽(うん)と閉じている。

前鬼と後鬼を従えた役行者小角像(四国第番札所・根香寺) |
後鬼の妙童鬼(みょうどうき)は、陰を表わす青色の鬼で、白面の顔に髪がかぶさり、口は阿(あ)と開いている。
手に大慈悲の理水が入っている瓶をもち、背中に種を入れた笈を背負っている。
小角は、前鬼と後鬼に、山中での修行者に仕える大切な仕事として、水を汲むこと、薪を拾うこと、食べ物を作ることなどを教えた。

前鬼と後鬼の子どもたち=男鬼の五人は、前鬼として、それぞれ五鬼熊は不動坊、五鬼童(五鬼堂)は行者坊、五鬼上(五鬼円)は中の坊、五鬼継(五鬼作)は森本坊、五鬼助は小仲坊という名で、山伏のために宿坊を構えて奉仕を続けた。
大峯修行の人々の道案内をしたり、宿の世話をしたりすることなどが、小角から言いつけられた。
男鬼五人の子孫は、後に、奈良県吉野郡下北山村にある「前鬼の里」に住みついた。
そして、彼らの子孫は、前鬼としての務めを受け継いでいった。

一方、後鬼は、奈良県吉野郡天川村洞川に住んだとされ、洞川(どろがわ)の人たちは、後鬼の子孫だといっている。
大峯から熊野への奥がけ修行に、前鬼の人は、深仙や釈迦ヶ岳、前鬼の裏行場への案内をする。
また、後鬼の子孫とする洞川の人は、山上ヶ岳や小笹の行場への案内をして、修行者のために仕えた。

奈良県吉野郡天川村洞川 |

役行者には、鬼の形をしていた義覚と義玄という弟子がいた。それで、この二人が、前鬼、後鬼だったとも伝えられている。
 |
|
[ micho7 さん ] は、実際に五鬼の子孫に会ったという。
五鬼物語 ( KOTOこれ
2006 ) |
|
 |
| |
解 説 |
|
|  |
山伏の格好は、不動明王をなぞらえた姿とされ、白衣、兜巾(ときん)、悟りを得る指針である六波羅蜜を示す丸い房を六つ付けた結袈裟(ゆいげさ;梵天袈裟ともいう。)を身に付け、両手にホラ貝、錫杖(しゃくじょう)をもつ。
修験道では、峯に入る際、この姿に着替えて、身なりを変える。これは、山中の厳しい修行によって、迷いの世界から悟りの世界に入って変身すること、つまり、即身成仏への道を歩む姿だとされている。
大峯への登山を何回も繰り返しているうちに、役行者小角が山中で修行した心に通じるようになって、自然に悟りが開けてくるってくるといわれている。

小角の教えは、特に何も書き残されてはいないが、心から心へ、口から口へ言い伝えられてきた。 |
|

山伏姿(四国・剣山の護摩供養)
|
「わがあとを継がんとする者は、十界頓超(じっかいとんちょう)の行をしなさい。行をすると、心身に付きまとって心を乱していたものがすべて離れてしまう。そして、必ず悟りに入ることができる。」と、修行者たちに教えている。

十界とは、人間が悟りを得るまでの間にあるとされる「十の世界」のことで、修行を重ねることによって、人間の迷いの世界から菩薩の世界へ移り、遂には仏の世界へ入れるという。
そして、これを速く達成するための行が、小角のいう「頓超の行」だとされている。
| 【 頓超の行 】 次の①~⑥を「六道の修行」という。 |
| ① 床堅(とこがため)地獄 |
自己に仏性があることを感じさせる修行法 |
| ② 懺悔(ざんげ)餓鬼 |
自己の罪を懺悔する。 |
| ③ 業秤(ごうはかり)畜生 | 修行者の罪や業を計る。 |
| ④ 水断(みずだち)修羅 |
水の使用や飲むことを一切禁止。 |
| ⑤ 人道行(懺悔) |
密室で先達と対して三業の罪過を懺悔告白する。 |
| ⑥ 相撲(すもう)天 |
修行者が相撲をとる。 |
| ⑦ 延年(えんねん)声明 |
長寿を祝う舞をまう。 |
| ⑧ 小木(こぎ)縁覚 |
修行者が採燈の先達に小木を納める。 |
| ⑨ 穀断(こくだち)菩薩 |
七日間、穀類を一切断って修行する。 |
| ⑩ 正勧請(しょうかんじょう)仏 |
修行者は、先達たちから大日如来の秘印が授けられ、即身成仏する。 |

修行者は、「懺悔、懺悔、六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と唱えながら、ただひたすら、山へ登る。
修験道とは、自分自身が山に登ることを通して修行を積むこと。苦しい山登りも、登山を重ねるに連れて心も体も鍛えられ、やがて仏の悟りを得られるようになるといわれている。
これが、今も伝えられている役行者の教えだという。

紀伊山地の霊場と参詣道 by 吉野観光HP |
|

役行者像が見守る
渡し跡(吉野町側) |
|  天の森総合サイト
天の森総合サイト

 天の森総合サイト
天の森総合サイト
